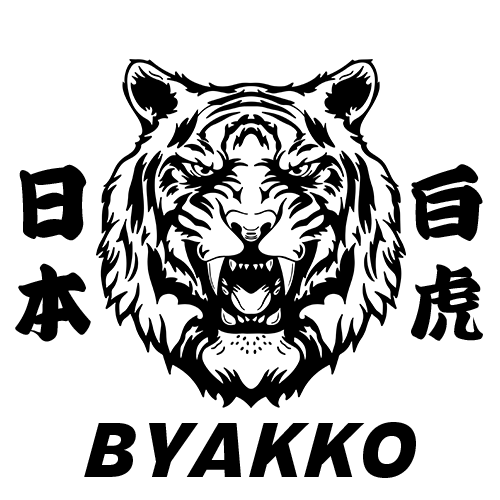和家具が見直される時代へ

和家具とは、日本人の生活様式や気候風土に合わせて発展してきた家具のことです。
洋家具が機能性や装飾を重視してきたのに対し、和家具は「暮らしに溶け込む静かな存在」として発達してきました。
近年では、北欧ミニマリズムとの親和性から「Japandi(Japanese + Scandinavian)」というスタイルが欧米で注目され、和家具が再評価されています。
素材、構造、佇まいのすべてに「無駄のない美」が宿り、サステナブルな価値観とも響き合っています。
和家具とは?

和家具とは、単に「日本製の家具」という意味ではなく、自然素材・伝統的木工技術・職人の手仕事によって生み出された、暮らしと一体化する家具を指します。
その起源は平安期の調度品に遡り、江戸時代には指物師(さしものし)たちが釘を使わずに木と木を組み合わせる「木組み」技法を確立しました。こうして生まれた家具は、金属を使わず木の伸縮を計算した緻密な構造により、100年以上の使用にも耐えうる耐久性を持ちます。
和家具の魅力は、機能と美の調和にあります。桐・欅・杉・檜など、湿度の高い日本の気候に適した国産木材が使われ、収納効率・通気性・軽量性が考慮された設計は、まさに「日常に寄り添う道具」としての完成形です。また、時間の経過とともに木目の艶や色合いが深まり、経年変化そのものが「美」として受け入れられる点にも、日本特有の感性が表れています。
他のアジア家具との違い
日本の和家具は、静けさと余白を尊ぶデザインである点が、他のアジア家具と大きく異なります。
たとえば中国家具は宮廷文化に根ざし、紫檀や黒檀などの重厚な木材を使い、金具や彫刻を施した「威厳」や「格式」を重んじるのに対し、
和家具はあくまで「暮らしの中に溶け込む存在」であり、目立たない美しさ=引き算の美学を大切にします。
韓国の韓家具もまた自然素材を生かしますが、日本の家具が持つ「軽さ」「可動性」「モジュール性(組み替えられる・重ねられる)」は独特で、狭い居住空間での実用性を追求した結果生まれた文化的デザインです。
また、東南アジアの家具が気候風土に合わせた開放的・ラフな作りを特徴とするのに対し、和家具は精緻な構造と繊細な手仕事で成り立っています。
「飾るための家具」ではなく、「使いながら完成していく家具」であること。これこそが、和家具を世界のどの家具文化とも異なる存在にしています。
和家具の代表例とその背景
|
家具名 |
特徴・歴史的背景 |
|
桐箪笥(きりだんす) |
江戸時代に誕生し、嫁入り道具として日本の家庭に広く普及しました。 桐は湿気や虫に強く、軽量で持ち運びもしやすいことから、着物保管に最も適した素材とされました。 「桐箪笥に仕舞えば、一生モノ」と言われるほど耐久性に優れ、代々受け継がれることも珍しくありません。 |
|
船箪笥(ふなだんす) |
江戸から明治にかけて、北前船の船乗りたちが財産や通帳を保管するために使っていた堅牢な箪笥です。 重厚な鉄の金具で装飾され、「鍵付き」「持ち運び可能」「防水性」など機能性も高く、職人技が光る逸品です。 |
|
水屋箪笥(みずやだんす) |
茶道文化や日本の台所「おくどさん」とともに発展した食器棚です。 上下に分かれた構造が特徴で、下段には大皿や鍋、上段には茶器や湯呑みを収納。 通気性・水切れを意識した設計で、機能性と美を兼ね備えています。 |
|
座卓・文机(ざたく・ふづくえ) |
畳文化から生まれた、床と一体化する低座スタイルの象徴。 家族が一堂に会して食卓を囲む「ちゃぶ台」もその流れにあります。 西洋家具のような「空間を支配する存在」ではなく、必要なときに出して使い、不要時は畳める柔軟さが特徴。 この「可変性」こそ、狭い住宅事情と共生してきた日本人の知恵を表しています。 |
|
行灯箪笥・薬箪笥(あんどんだんす・くすりだんす) |
行灯箪笥は照明器具と収納を兼ねた機能的家具、薬箪笥は商人や医師が薬草や道具を整理するために用いたものです。 小さな引き出しが無数に並ぶその姿は、日本人の几帳面な整理文化の象徴でもあります。 |
和家具に宿る哲学 ―「用の美」と「侘び寂び」

和家具には、西洋家具のような派手な装飾や対称性はありません。
その代わりに、素材そのものの質感や木目、年月を経て現れる色艶、傷跡までもが“美”として受け入れられています。
これは日本の伝統的な美意識である「用の美」(民藝運動で提唱された、日用品の中にある実用と美の調和)や、「侘び寂び」(不完全さや儚さの中に美を見出す感性)と深く結びついています。
「華やかさより静けさを」「新しさより深みを」「完璧より味わいを」
和家具は、そんな日本人の美学を形にした存在です。
また、木の香りや手触り、使うほどに馴染む感覚は、自然と共生する暮らしの象徴でもあります。
西洋の家具が「空間を飾るためのアート」であるのに対し、和家具は「人の暮らしの中で呼吸する道具」。見せるためではなく、使う人とともに時間を重ね、人生を語る家具です。
こうした思想は、現代の「サステナブルデザイン」や「ロングライフプロダクト」の考え方にも通じます。和家具は決して古いものではなく、「自然と調和し、長く使い、愛着を育てる」という最先端の価値観をすでに体現している家具文化なのです。
和家具の衰退と再評価
高度経済成長期以降、和室から洋室中心の住まいが増え、家屋の間取り・住宅文化が変化する中で、和家具の需要は徐々に減少しました。
環境省の調査「データで見る消費者とリユース」(平成27年度)によれば、不用品カテゴリとして「家具類」が21.1%と報告されており、衣類・服飾品(ブランド品を除く)も高頻度で不要化する傾向が見られます。 環境省
多くの和家具が、「重くて運びづらい」「譲渡先を見つけにくい」という物理的・流通上の制約により、市場には出づらく、処分されるか家庭で眠るケースも散見されます。
その一方で、海外では“Japanese Antique”や“Wabi-sabi Interior”という文脈で和家具がインテリア愛好家から注目されるようになりました。「京指物」「指物」の工芸技術を扱う伝統工芸の説明において、釘を使わずに木と木を巧みに組む技法(ホゾ・継ぎ手等)が強調され、これが和家具の構造的・美的価値の根幹とされています。こうした動きは、単なる趣味性の高まりではなく、「ものを大切に長く使う価値観の再評価」の潮流と共鳴しています。
和家具のこれから
和家具の魅力は、流行に左右されない普遍性にあります。桐箪笥や座卓など、丁寧に作られた和家具は、何十年、時には百年を超えて使い続けることができます。
使い手が変わっても、手入れをしながら大切に使うことで、木の色艶や質感が深まり、「経年美」という唯一無二の価値が生まれます。
現代社会では大量生産と消費のスピードが加速し、家具が「使い捨て」になりがちです。しかし、和家具はその対極にあります。「壊れたら直す」「飽きても捨てない」という日本人の暮らしの知恵と美意識が、そこに息づいています。
今、世界では「サステナブルデザイン」「ロングライフプロダクト」が注目されています。和家具はまさにその原点。職人が自然素材と向き合い、丁寧に仕上げた家具は、環境への負荷を抑えながら、世代を超えて愛される存在です。
和家具の未来とは、新しく作ることではなく、良いものを長く使い続ける文化を次世代につなぐこと。
それは、日本人の美意識と暮らしの知恵が融合した「持続可能な豊かさ」の象徴なのです。