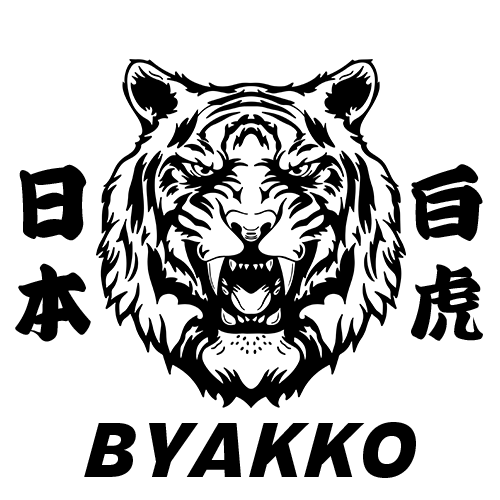木工について
スギやヒノキ、桜などの木材を用いて作られる木工品は、森林の多さから木が豊富な日本で様々な身の回りのものの材料となってきました。現在、日本の面積のおよそ7割が森林だといわれています。
そんな中でも日本で古来から現代まで私たちの暮らしとともに寄り添ってきた木工。日本国内のみならず海外にも人気を博している木工品や木造建築がどのように使われているのか、そして様々な伝統工芸品などについてご紹介します。
衣食住に寄り添う木工
木材は、縄文時代(~紀元前10世紀ごろ)よりも前から使われていたと考えられています。建築や生活用品などに活用されていました。現代でも実際に様々な木工品が愛されています。今回は生活の必需品を指す慣用句である「衣食住」に沿って木工品を紹介します。
衣

衣服の収納や保管に関する木工製品としては、箪笥や下駄箱などがあげられます。特に箪笥は釘を使わずに板材や金属の棒を精密に組み合わせる「指物(さしもの)」という技法を基礎として作られており、匠の技術の集結により、木目の美しさと湿気やカビを防ぎながら衣類を美しく保管するための実用性を両立させています。
また、日本では江戸時代の着物文化から明治時代以降に洋服文化に移り変わるにつれて、コートをかけるためのハンガーなども一枚板などから切り出す形で普及していきました。当時は平らなハンガーが主流な中、徐々に立体的な洋服を綺麗に保管するためにハンガーも立体的に変わっていきました。
食
椀や盆、箸などの食器や、しゃもじやへら、木型やせいろなどといった調理道具においても木工品が活用されています。食に関するワンシーンにおいて木の香り高さや柔らかさは時代を超えて長く愛されているのです。

蒸し器のひとつである木や竹製のせいろ(蒸籠)について、江戸時代以前は曲物や桶の形の木製の甑(こしき)と呼ばれる蒸し器が使われていましたが、江戸時代になって以降せいろが発達したと言われています。湯のたぎっている釜やかまどの上に乗せて湯気で食物を蒸すため、熱の伝わり方がゆるやかであることから食物のもつ旨味が保たれるとされています。さらに近年の日本でもSNSがきっかけにせいろ蒸しブームが広がっており、手持ちの野菜や魚、肉、ごはんなど、様々な食材を一気に調理できることから再注目されています。
住

木造建築はそのあたたかみや足触り、手触りの優しさ、仄かな木の香りから古来から現代まで、変わらず人気の建築方法です。木自体の持つ調湿性能などの粘り強さや、加工のしやすさが元々のきっかけであったとされていますが、実際に寺社仏閣などでは一部修繕を繰り返しながら1000年以上の時を経てもその姿を保っている建造物が日本にはいくつもあります。
また、家庭において利用される家具なども木製のものが多く利用されています。家の中に一つは木製の家具がある人も多いのではないでしょうか。日本だと扉や机、こたつや棚、障子などに多く利用されており、前述したとおり加工のしやすさや風合いの幅広さから様々なインテリアに活かされています。
木材ごとの特徴
スギ
日本の本州から九州地方まで分布し、地面からまっすぐ成長する特性がある木材です。加工した際の木目も直線的で美しいとされ、フローリングなどの建具に多く活用されています。さらに、通気性や防水性が高い性質も持っており、古くから酒樽や造船の原料にもなっています。
内部には空気が含まれているため木材の中でも軽量で、空気に触れることで色合いの経年変化も楽しめます。
ヒノキ

高級感がある繊細な木目が特徴の木材です。色合いは明るく、香りが優れている点も大きなポイントとされています。その香り高さは
防虫性能の高さなどから保存性や耐久性が高い木材でもあり、日本でも最古の木造建築とされている法隆寺にも使用されています。さらにヒノキの香り高さによるリラックス効果を得るためにヒノキ風呂やヒノキ酒器など、活用の幅がかなり広い木材のひとつです。
桐

主に北海道南部から本州にかけて分布している木で、伐採してもすぐに枝が伸びることから「切る」「切り」とかけて「桐(きり)」という名前の由来となったとされています。色合いは木材の中でも明るめの白色です。
寒冷地で育つ桐ほど密度が高く上質な木材になることから、高級木材のひとつに数えられます。主に桐箪笥や琴などの楽器に活用されており、桐材の内部は蜂の巣のような空洞が無数に存在していることから保湿性が高く、乾燥している際には内部に含んだ水分を放出する特徴を持ち合わせており、湿度を一定に保つ調湿性能や防火性も高い木材です。
桜

日本国内をはじめ、北半球の国に自生している木であり、日本では3月から5月にかけて桜前線が南部から北上し、美しい薄ピンクの花を咲かせます。この時期は花見シーズンとして国内外からも多くの観光客が日本を訪れるシーズンでもあります。
主に家具や美術品、楽器などの原料として活用されることが多い木材ですが、実際に木材として活用できる品種には限りがあるため、貴重な材料です。桜ならではの華やかな香りも特徴の一つで、固い材質ながら加工がしやすい点も重宝されています。材質の固さもさることながら、密度も高い木材であり、フローリング材として活用することで長持ちするという実用面の高さも持ち合わせています。
伝統工芸
寄木細工

様々な木の色合いや風合いを組み合わせて模様を作り出した種板(たねいた)と呼ばれる板をベースに作られる木工品です。主な特徴は、種板をうすく削ってシート状のようにしたものを化粧材として貼り付ける「ヅク貼り」と、種板そのものをろくろでくりぬいて加工する「ムクづくり」の2つの製法です。寄木細工において生み出される伝統模様は着物などにも使われる「七宝」や「市松」などのおよそ60種類以上とされており、色や配置を変えることでその種類はさらに多くなります。
江戸時代(~1868年)後期に箱根で誕生し、木の種類が豊富な箱根の山の特性に着目することで、色や木目の異なる木を寄せ合わせて箱やお盆を作ったことが起源だとされています。
また、寄木細工においては「秘密箱」というものもあります。こちらは寄木細工の箱に開く順番などのからくりがしこまれており、それを解除しなければ開かない仕組みとなっている箱で、正確な起源は不明ですが1700年台後半には存在したとされており、元々は宝石などの貴重品を収納するためのものであったとされています。

曲げわっぱ

「わっぱ」とは輪の形をした入れ物のことを指しています。伝統的な木工技法である「曲物(まげもの)」の技術を活かし、杉などの薄い板を曲げ、山桜の木の皮で継ぎ目を縫い留めて底や蓋をつけた入れ物です。形も様々で、お弁当箱のような形から、お盆や籠のような形のものまで、曲物の技術を活かした木工品を広く「曲げわっぱ」と呼んでいます。
代表的なものは秋田杉を使った「大館曲げわっぱ」で、素材には年輪の幅がほぼ同じ間隔でできている秋田杉の柾目(まさめ)を使います。元々曲げわっぱが生まれたきっかけになったのも秋田杉であるとされ、軽くて弾力性に富んでいることから曲物に活用され、1600年台後半に
・柾目(まさめ) - 年輪に対して直角に切ったときにまっすぐ並ぶ木目のこと
大阪欄間

日本家屋において、部屋と部屋の境目において天井と鴨井の間に取り付けられる部材「欄間(らんま)」において、大阪府大阪市や岸和田市、吹田市周辺などで作られているものを指します。美しい彫刻や透かし彫りなどがあしらわれており、特に立体的に彫りこんで模様や絵柄を浮き上がらせる「彫刻欄間」は、天然木の木目を活かしながら手間をかけており、大阪欄間の代名詞に数えられます。
その制作工程は古木の選定から実際の彫り、実際に欄間を組み込む額縁組まで多岐にわたり、それらが繊細な美しさと重厚さを兼ね合わせた美しさを演出してくれるのです。
また、美しさだけではなく実用性も備えています。欄間自体は採光と通気を行うことを目的としていますが、大阪欄間における多様な技法はどれもその役割を担っています。
・鴨居(かもい) - ふすまや障子などの引き戸を取り付ける枠材の上部にあたる部材のこと。
まとめ
今回は、木工がどのように私たちの生活に関わっているのか、そして日本文化において木工を中心とした伝統工芸はどのようなものがあるのかについてご紹介しました。
一見、美しさや遊び心をたずさえたものでも実用性を兼ね備えていることも多くあり、それが現代まで変わらず愛されていたり、新たなものを生み出すための知恵やアイデアの糧になることもあります。伝統的な技術や文化は、これからも間違いなく変わらずに愛されるもののひとつであり、今ならではの視点との化学反応も楽しみですね。