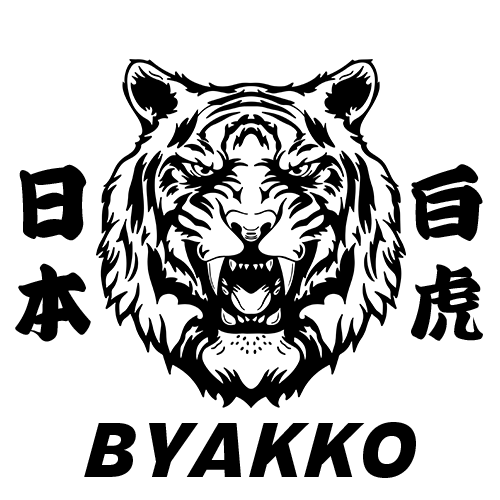日本の伝統技術「挽物(ひきもの)」とは?

引用:興栄産業㈱ | 庄川木工挽物会|伝統的工芸|庄川挽物木地
美しさと機能性を兼ね備えた木の工芸品を、世界へ
日本には、長い年月をかけて磨き上げられた多くの伝統工芸があります。その中でも「挽物(ひきもの)」は、木材を回転させて削ることによって生み出される、美しさと機能性を兼ね備えた木工技術です。主に椀(わん)や盆(ぼん)、鉢、カップ、家具の脚などの円形・円筒形の製品を作るために用いられ、実用性と芸術性を両立した工芸品として、国内外で注目を集めています。
本記事では、「挽物とは何か?」という基本から、制作工程や道具、代表的な産地、インテリアへの応用、そして海外における人気まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧にご紹介します。
挽物とは? ─ 木を「引いて」形を作る技術
「挽物」は、木材をろくろで回転させ、刃物を当てながら削っていく技法です。"引く"という表現は、木材を回しながら自分の方向に削っていく動作に由来します。出来上がる形は、曲線が滑らかでシンメトリーなものが多く、手に持ったときの質感やバランスの良さが魅力です。
また、同じろくろ技術を用いる「陶芸」とは異なり、素材が木であるため、温かみや木目の美しさ、軽さ、強度といった木ならではの特性が製品に反映されます。そのため、使うたびに自然素材ならではの風合いが深まり、経年変化も楽しめる点が特徴です。
歴史と起源
挽物の起源は非常に古く、奈良時代にはすでに存在していたと考えられています。法隆寺に残る木製品や、漆器などにその技術が見られ、寺院や武家の生活道具として重宝されていました。
中世には仏具や神具、茶道具などとしても発展し、やがて江戸時代には庶民の間にも広まりました。茶碗や汁椀などの日用品として家庭に根付き、各地でろくろ細工を生業とする「木地師(きじし)」が活躍するようになりました。
明治以降、近代化の波により機械化が進みましたが、今なお手仕事による製品も多く、伝統と革新が共存する分野として世界から高い評価を受けています。
挽物の制作工程 ─ 丁寧な手仕事と自然との対話
挽物の制作は、素材選びから仕上げまで丁寧な工程を経て行われます。
-
木取り(素材の選定) ケヤキ、トチ、クスノキ、ホオノキなど、日本産の広葉樹が中心。年輪の美しさ、木肌のなめらかさ、加工のしやすさを見極め、職人が一本一本を厳選します。
-
自然乾燥 木材は伐採後すぐには使用できません。数ヶ月から数年をかけて自然乾燥させ、内部の水分をじっくり抜くことで、ひび割れや変形を防ぎます。乾燥中に現れる木のクセや表情も重要な判断材料です。
-
荒挽き(粗削り) ろくろを使って大まかな形を作ります。余分な部分を取り除きながら、最終形のイメージに近づけていきます。この段階での技術の差が、後の仕上がりに大きく影響します。
-
仕上げ挽き 完全に乾燥した木材を改めてろくろにかけ、最終的な形状に仕上げます。繊細なカーブや薄さを保ちながら、バランスの取れた形状に削るには、経験と感覚が不可欠です。
-
磨きと塗装 表面を布やサンドペーパーで丁寧に磨き、漆、蜜蝋、植物性オイルなどを使って塗装します。これにより耐久性が増し、深みのある艶が加わります。漆塗りは、何度も塗って乾かすという工程を繰り返すため、非常に手間がかかります。
挽物に使われる道具 ─ 手仕事を支える匠の道具たち
挽物には、「手ろくろ」「足踏みろくろ」「電動ろくろ(旋盤)」といった回転装置が使われます。木を回転させる力を安定させ、精密な加工を可能にする重要な道具です。
削るための「バイト」と呼ばれる刃物は、市販のものもありますが、多くの職人は自らの手で改良を加えたり、一から手作りすることもあります。木材の種類や用途に応じて数十本のバイトを使い分ける職人もおり、道具の扱いもまた技術のひとつとされています。
代表的な産地とブランド
代表的な産地とブランド
-
静岡挽物(静岡県):江戸時代から続く伝統。駿河地方では、家具の脚部や香炉、花器など、用途も多様。現在では機械と手仕事を組み合わせた製造方法で、国内外に多く出荷されています。
-
庄川挽物(富山県):木地師の技術が生きる産地。木の乾燥に特にこだわり、狂いの少ない美しい製品を生み出します。茶道具や高級椀、飾り皿などに利用されています。
-
今市の挽物(栃木県):日光東照宮の門前町として栄えた今市では、仏具や民芸品の製作が盛ん。現在でも手ろくろを使った伝統的な技法が残り、多くの職人が活動しています。
挽物を使ったインテリア ─ モダンな空間に自然と調和する伝統美
挽物は、日用品や食器だけでなく、インテリアにも多く活用されています。円形や曲面の美しさを活かしたデザインは、和室はもちろん、現代のミニマルな洋風インテリアとも相性が良く、世界中の建築家やデザイナーに注目されています。
● ランプシェード・照明器具としての挽物

挽物で作られた木製のランプシェードは、木目を透かした柔らかい光を室内に届けてくれます。
特にクスノキやトチノキなどの広葉樹は光を柔らかく包むため、自然な雰囲気を演出できます。北欧家具と合わせても違和感がなく、温かみのある空間を作ることができます。
● 木製フレーム・ミラー・時計
精巧な挽物技術を応用した、丸型ミラーの木枠や、曲線を活かした掛け時計は、玄関やリビングのアクセントに最適です。漆塗りで深みのある艶を加えることで、より高級感のあるインテリアとなります。
● テーブル脚や椅子の構造部品

円柱状のパーツが多いテーブル脚や椅子の支柱部分には、挽物がよく使われています。職人が手作業で削り出すことで、機械製品にはない滑らかさと温もりが生まれます。特にナチュラル系の木製家具や、和洋折衷スタイルの空間におすすめです。
● ウォールデコレーションやアートパネル
最近では、挽物を立体的なアートとして壁面に飾る事例も増えています。たとえば、複数の円形パーツを組み合わせて「木の幾何学模様」として構成し、シンプルな白壁にアクセントを与えるようなデザインが海外でも人気です。
● 花台・プランター・小型棚
木の質感と相性の良い植物と組み合わせたプランター台や小型の棚も、挽物による優雅な曲線が生かされるポイントです。リビングや玄関に設置することで、空間に自然なリズムと温もりが加わります。
海外での人気と取り入れ方
挽物は、欧米を中心に「Japandi」スタイルの人気とともに注目を集めています。「侘び寂び」や「木のぬくもり」といった日本の美学が、ミニマルで自然志向の欧州インテリアと共鳴しているのです。
-
素材の持つ自然性:環境への配慮や自然回帰の潮流と相性が良く、プラスチックに代わる持続可能な素材として支持されています。
-
職人技への敬意:大量生産では再現できない手仕事の魅力が、アートやクラフトとしての価値を高めています。
-
異素材との融合:ガラスや金属と組み合わせたデザインも人気で、現代的な印象を与えつつ、木の温かみも損なわない製品が多く登場しています。
まとめ:暮らしに挽物を取り入れてみませんか?
挽物は、日本の自然と職人の技が生み出す、実用性と芸術性を兼ね備えた伝統工芸です。使い込むほどに味わいが増し、日常の中で五感を通して自然を感じることができます。
初心者でも手軽に取り入れられる器や照明から始めてみることで、暮らしに小さな感動と豊かさをもたらすでしょう。
日本の伝統を未来へつなぐ意味でも、そして世界に誇れるクラフト文化としても、挽物の魅力をもっと多くの人に伝えていく価値があります。